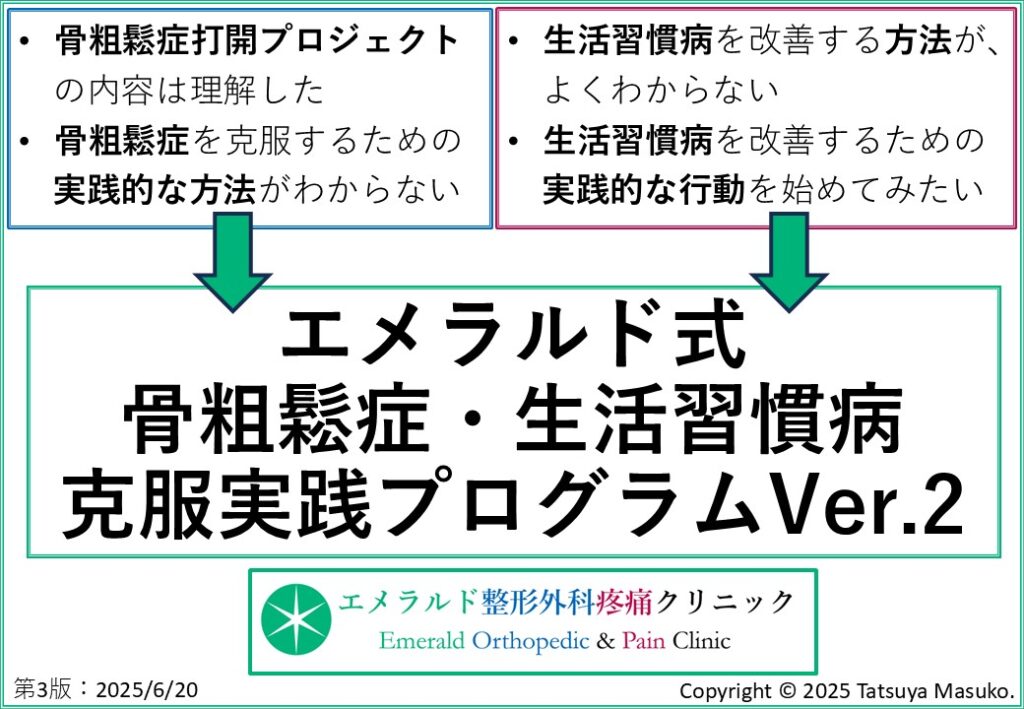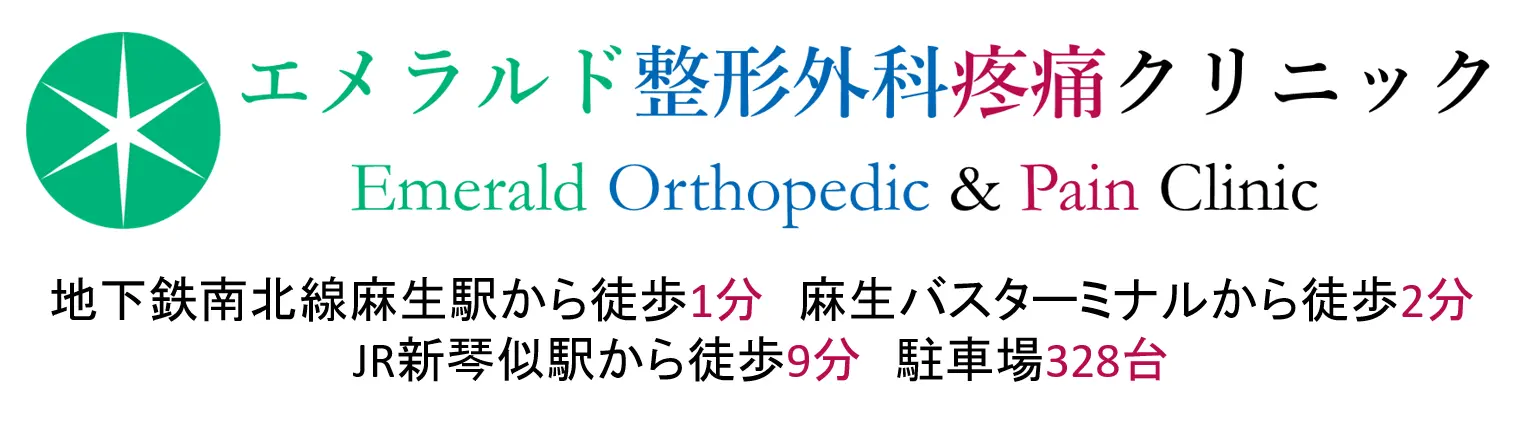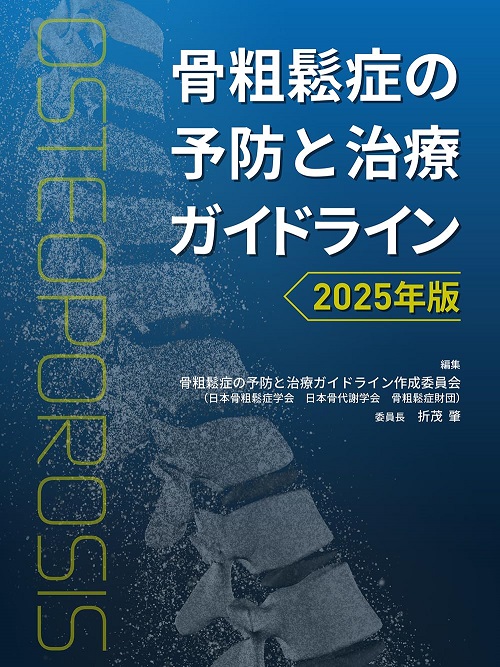
10年ぶりの改訂
2025年8月に、実に10年ぶりに骨粗鬆症ガイドライン(正確には、骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン)が改訂されました。
前回と比較し、評価できる部分もありますが、あまり評価できない部分もあります。
薬物治療について
この10年間の間に、ロモソズマブ(イベニティ®)、ゾロドレン酸(リクラスト®)、アバロパラチド(オスタバロ®)など、新しい骨粗鬆症薬が次々に使用可能となり、それらの有効性が骨粗鬆症ガイドライン2025年版では評価されています。
具体的には、
A. 骨密度上昇効果
B. 骨折抑制効果
の2点について評価がされています。
評価項目
評価項目には、原著では、
①合意率
②エビデンスの強さ
③推奨の強さ
の3つが記載されています。
「合意率」は、最高が100%であり、100%に近いほど良いことになります。
「エビデンスの強」さは、AからDに分けられ、Aが最も強いエビデンスがあります。
「推奨の強さ」は、原著では文章として記載されており、「処方を推奨する」・「処方を提案する」・「処方しないことを提案する」の3つ(院長が独自に作成した下表では、それぞれ、1・2・3と表記)で、「A. 骨密度上昇効果」と「B. 骨折抑制効果」では基準が異なります。
「A. 骨密度上昇効果」
「A. 骨密度上昇効果」については、ガイドラインを一読すれば理解ができる内容となっており、誤解を招く恐れはほぼありません。
具体的には、「合意率」が100%で、「エビデンス」の強さがAで、「推奨の強さ」が1の薬剤が、使用することが望ましい薬剤となります。
なお、ロモソズマブ(イベニティ®)は、唯一、「強く推奨」と文章で記載されているため、特別に「S」と表記しています。
「B. 骨折抑制効果」
「推奨の強さ」の記載は、誤解を招く内容となっている
残念なことに、「B. 骨折抑制効果」の「推奨の強さ」については、薬物の効果に対する評価がかなりわかりづらく、骨粗鬆症についてあまり詳しくない医師や一般の方は、ガイドラインを一読しただけでは、内容を誤解してしまう可能性があります。
具体的には、薬剤による骨折抑制効果の「推奨の強さ」は「処方を推奨する」、「処方を提案する」、「処方しないことを提案する」の3段階で評価されていますが、この文言だけでは、「処方を推奨する」も「処方を提案する」も両方とも有効であると考えてしまい、「処方を推奨する」の薬でも、「処方を提案する」薬でも、「どちらでも良い」と考えてしますでしょう。
「処方を推奨する」と「処方を提案する」には明白な違いがある
しかしながら、真実は違います。
実は「処方を推奨する」と「処方を提案する」には明白な違いがあります。
具体的には、「処方を推奨する」は、
・椎体
・大腿骨近位部
・非椎体
の全てに骨折抑制効果があることを意味します。
それに対し、「処方を提案する」は、これら3つのうちのどれかで骨折抑制効果がないことを意味します。
つまり、その薬剤はこれら3つのうちのどれかには効かないということであり、たいていの場合は、最も生命の危険性が高い大腿骨近位部に対する効果がありません。
3つの骨折すべてに抑制効果がある薬剤が望ましい
ある程度若い年齢である40代~50代の方であっても、軽微な外傷で大腿骨近位部骨折を起こすことがあり、実際にクリニックでも治療経験があります。
そのため、骨粗鬆症の治療をするのであれば、骨密度上昇効果は当然として、椎体・大腿骨近位部・非椎体の3つの骨折全てに抑制効果がある薬剤が望ましいと考えることは、至極当然です。
わかりやすい表を作成
前回のガイドライン2015年版では、これら3つの骨折に対する骨折抑制効果が明記されていましたが、ガイドライン2025年版では、前述のようにわかりづらくなってしまいました。
そのため、多くの方がわかりやすく、誤解を招かないようにするために、ガイドライン2025年版の内容をわかりやすい表にまとめてみました。
なお、「推奨の強さ」は、
・「処方を推奨する」は1
・「処方を提案する」は2
・「処方しないことを提案する」は3
として表記しています。

ガイドライン2025年版の結果から導き出されたお勧めの薬5種類
前述のように、骨粗鬆症の治療をするのであれば、骨密度上昇効果が良いことは当然として、椎体・大腿骨近位部・非椎体の3つの骨折全てに抑制効果がある薬剤、つまり1の薬剤が望ましいと言えます。
そのような薬剤は、
・アレンドロン酸
・リセドロン酸
・ゾロドレン酸
・デノスマブ
・ロモソズマブ
の5種類しかありません。
ですから、実際に薬剤で骨粗鬆症の治療をするのであれば、これら5種類の薬剤のなかから状況や病態に応じて選択することが適切であると言えます。
栄養療法について
「骨粗鬆症の治療戦略の柱として重要」
栄養療法は、運動療法とともに「骨粗鬆症の治療戦略の柱として重要であることに異論はない」と記載されています。
ほぼ、カルシウムとビタミンDについて記載しかない
しかし、前回の『ガイドライン2015年版』と同様に『ガイドライン2025年版』も、カルシウムやビタミンDの記載が主で、それ以外の栄養素についての記載は極めてわずかでした。
CQ2:骨粗鬆症患者の治療に対し、カルシウム、ビタミンDの摂取量はどの程度が推奨されるか?
CQとは「クリニカルクエスチョン」のことで、『ガイドライン2025年版』で使用されている、治療上の問題提起です。
そして上記の結論は、
・骨粗鬆症の患者に対し、カルシウムを700~800mg/日、ビタミンDを15~20μg/日(600~800IU/日)摂取することを提案する
・合意率:93.8%
・エビデンスの強さ:C
・推奨の強さ:2
と記載されています。
ここで大切なことは、エビデンスの強さがCだということです。
つまり、骨粗鬆症の治療にとって、カルシウムやビタミンDを単独で使用することは有効ではないということです
カルシウムとビタミンDを併用することは有効
カルシウムとビタミンDを同時に摂取することは、骨折リスクを低下させることができることが報告されています。
(Tang BM et al. Lancet 2007;370:657-666.)
(Chakhtoura et al. J Clin Endocrinol Metab 2022;107:882-898.)
カルシウムサプリメントの摂り過ぎは危険
カルシウムサプリメントの摂り過ぎは健康障害を引き起こす可能性があることが記載されています。
(Bolland MJ et al. BML 2008: 336:262-6.)
(Bolland MJ et al. BML 2010: 341:c3691.)
ビタミンDは体内で合成可能
ビタミンDと日光浴に関しては、「ビタミンDは紫外線にあたることで皮膚でも合成されるので、適度な日光曝露暴露が必要である。」と2行のみの記載です。
そのほかの栄養素
ビタミンK、B6、B12、葉酸については、わずかに記載がある程度です。
運動療法について
「骨粗鬆症の治療戦略の柱として重要」
運動療法は、栄養療法とともに「骨粗鬆症の治療戦略の柱として重要であることに異論はない」と記載されています。
ガイドラインでは、「運動療法は、荷重や筋力による力学的負荷による骨密度上昇効果や身体機能(筋力、身体バランス、椅子立ち上がり時間、歩行速度など)の改善による転倒予防効果が期待される」と記載しています。
また、主な運動の種類としては、「有酸素運動、筋力トレーニング、その複合運動、ウォーキング、荷重運動、太極拳、全身振動刺激運動、水中運動」を挙げています。
CQ3:骨粗鬆症患者の骨折予防に運動療法は推奨されるか?
上記のクリニカルクエスチョンに対する結論は、
・骨粗鬆症患者の骨折予防に運動療法を実施することを提案する
・合意率:100%
・エビデンスの強さ:B
・推奨の強さ:2
と記載されています。
骨密度上昇効果
閉経後の高齢女性(60~82歳)に対して、運動は腰椎、大腿骨頚部、大腿骨転子部の骨密度を上昇させた。
(Hejazi K et al. Arch Osteoporosis 2022; 23:39-51)
閉経後および高齢女性(51.4~79.3歳)に対して、高強度運動(インパクトエクササイズ、筋力トレーニングなど)は、腰椎骨密度を上昇させるが、その複合運動が効果的である。
(Kistler-Fischbacher M et al. Bone 2021; 143:115697.)
50歳以上の成人において、太極拳は腰椎骨密度を上昇させる。
(Zhang Y et al. Clin Interv Aging 2019;14:91-104/)
転倒予防効果
高齢者において、運動は転倒外傷、治癒を要する外傷、骨折の発生率を低下させる。
特に転倒リスクの高い高齢者や骨粗鬆症高齢者では、運動の有効性が高い。
また、バランストレーニングを含むプロトコールが転倒外傷予防に有効である。
(Zhao R et al. BMC Geriatr 2019; 19:341.)
骨折予防効果
50歳以上の成人(54~80歳)において、運動(骨強度上昇プログラム、転倒予防プログラム)は主要骨粗鬆症骨折の発生率を低下させた。
(Hoffmann I et al. Osteoporosis Int 2023;34:15-28.)
45歳以上の成人(45~95歳)において、運動は骨折発生数を減少させる。
しかし、椎体骨折発生数については、有意な効果は得られなかった。
(Kemmler W et al. Osteoporosis Int 2013; 24:1937-1950.)
エメラルド整形外科疼痛クリニックの取り組み
エメラルド整形外科疼痛クリニックでは、『骨粗鬆症ガイドライン2025年版』に基づき、薬物による治療だけでなく栄養指導や運動指導を実施するだけでなく、骨粗鬆症の予防を含めて各種の啓蒙活動も行っています。
具体的には、クリニックでは、
・『骨粗鬆症打開プロジェクト』を配布し、詳細を説明
・書籍『骨粗鬆症治療の真実と7つの叡智®』を用いて要点を説明
・場合により、『エメラルド式骨粗鬆症・生活習慣病克服実践プログラムVer.2』についての解説
を行っています。
また、ホームページ上では、
・骨粗鬆症の検診である『骨の健康チェック』を勧める
・骨粗鬆症薬の最も有名な副作用である「顎骨壊死と抜歯の対応」について解説
・最も深刻な現実である、「骨粗鬆症の適切な治療を行っても骨密度が改善しないこと」について解説
・脳機能の向上など「運動の真価」について解説
・『7つの叡智®~超健康と長寿の秘訣~』の『4. 東西栄養学の粋』に基づいた「適切な食生活」について解説
などを行っています。
拙著『骨粗鬆症治療の真実と7つの叡智®』
院長は、『骨粗鬆症治療の真実と7つの叡智®~超健康と長寿の秘訣~』を出版し、骨粗鬆症の原因、薬物治療の詳細、さらには栄養療法・運動療法についても詳しく説明するだけでなく、多くの医師にも知られていない「骨粗鬆症の真実」についても解説しています。
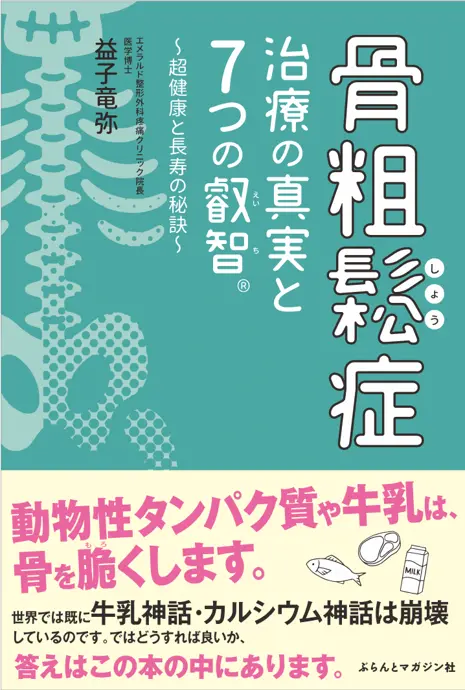
『7つの叡智®~超健康と長寿の秘訣~』
院長は、「健康」についての情報があまりに膨大に存在し、さらに情報自体が「玉石混淆」であり、「玉」に値する優れた情報である「叡智」を探し出すことが極めて困難となっている現状を憂慮し、現状を打開するために「7つの叡智®~超健康と長寿の秘訣~」を作成し、10年以上前から、その一部を公開しています。
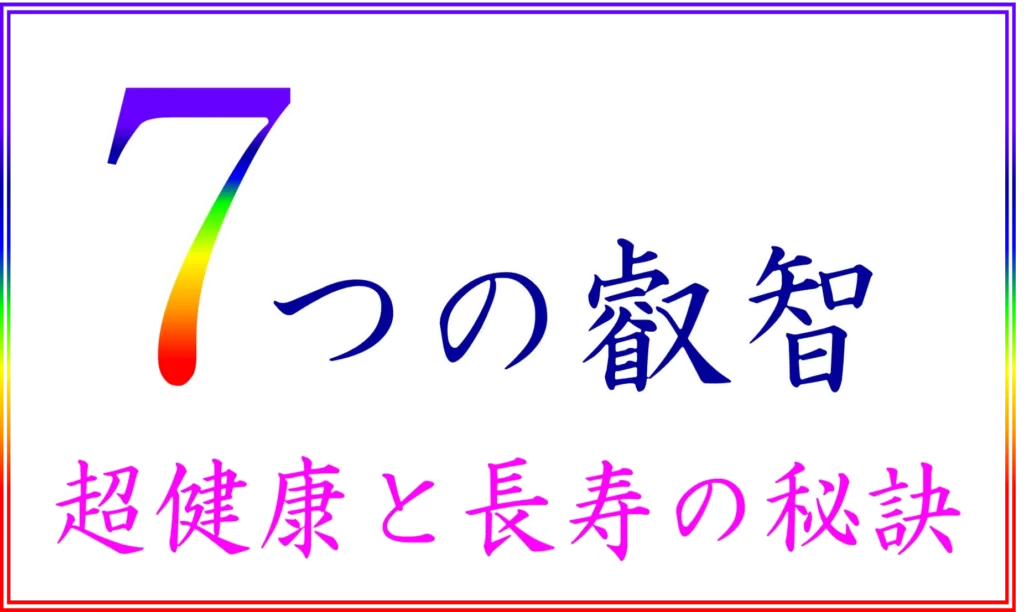
『7つの叡智®~超健康と長寿の秘訣~』の詳細
「7つの叡智®~超健康と長寿の秘訣~」は、
・古来より脈々と受け継がれている知識体系から最新の情報まで
・洋の東西を問わず
・多くの情報を入手・精査
・信頼性の極めて高い「玉」の情報のみ選定
・極めて広範囲の領域の「玉」の情報を総括
・超健康と長寿の秘訣として体系化
・7つの項目に分類
しています。
7つの項目
7つの項目は、
1. 世界の長寿地域
2. チャイナ・プロジェクト
3. 東洋医学と西洋医学
4. 東西栄養学の粋
5.最上の薬
6. 最新の遺伝子研究
7.脳科学と量子論
です。
『7つの叡智®~超健康と長寿の秘訣~』の詳細は、クリニックホームページや『7つの叡智®』のホームページをご覧ください。

『エメラルド式骨粗鬆症・生活習慣病克服実践プログラムVer.2』
エメラルド整形外科疼痛クリニックでは、骨粗鬆症だけでなく、高血圧・高脂血症・糖尿病などの生活習慣病も改善・克服するために、「知識」・「行動」・「継続」の3つの輪を実現した『エメラルド式骨粗鬆症・生活習慣病克服実践プログラムVer.2』を考案しました。
なお、「継続しやすくなるための試み」として、「行動」の結果を医学的に視覚化することで、モチベーションが維持しやすくなると考え、骨密度に加えて、脂肪量・筋肉量、血管年齢を医療機器で定期的に測定し、現状を把握することでモチベーション維持に繋げています。